12月
12:00-18:00
27日(土)
1月
12:00-17:00
1月10日(土)ー20日(火)まで、石井直人展を開催しております。
14日(水)は休廊します。
ー
12:00-18:00
24日(土)25日(日)
31日(土)
お知らせ
12月
12:00-18:00
27日(土)
1月
12:00-17:00
1月10日(土)ー20日(火)まで、石井直人展を開催しております。
14日(水)は休廊します。
ー
12:00-18:00
24日(土)25日(日)
31日(土)

雲南省 鶴慶県の龍珠村と霊地村で、白(ペー)族の人々によって伝統的に作られてきた「白棉紙(はくめんし)」を用いた活版印刷のカレンダー。今年の8月にgwen chanさんが雲南省を旅し、出合った手漉きの紙で制作されています。
この紙はカジノキ (BROUSSONETIA PAPYRIFERA)の皮から作られ、その起源は7~10世紀の唐代にまで遡ります。明代の朱応星による著作「天工開物」の中で、カジノキの皮から作られた紙は「棉紙」と記されており、これは古代中国で広く用いられていた呼び名です。白(ペー)族が生み出す紙は、山の湖き水を使用する製紙工程によって、ひときわ白く、通常の「棉紙」と容易に区別できます。伝統的には、サボテンや松の根が糊として用いられてきました。一枚一枚、手触りと風合いが際立った手漉きの紙です。印刷は、ベトナムの活版印刷工房にて行われています。月ごとに紙が変わり、新月と満月が記されています。
gallery白田にてご紹介しております。
soma folk
2026 letterpress paper mulberry calender yunnan china
サイズ:40×6cm
価格:8400円






11月
12:00 – 18:00
1日(土)2(日)
8日(土)9日(日)
22日(土)23日(日)
29日(土)30日(日)

金工作家の金森正起さん、文筆家の林琪香さんが、数年の時を経て、自ら造られた瀬戸の民家の文化施設。
初の展覧会に参加させていただきます。ものをつくる視点から視える手仕事のあり方、感じ方を、発信してくださる貴重な場が新しく誕生いたしました。これからの活動に期待を感じます。ご高覧賜りますようお願い申し上げます。
開館記念展
10月19日(日)〜12月20日(土)
11:00〜17:00(金曜・土曜)
石井すみ子(あゐ)
石井直人(陶芸)
大室桃生(パートドヴェール)
小澄正雄(和硝子)
小林徹也(陶芸)
土屋美恵子(織)
中西洋人(木彫)
日置路花(書)
金森正起(鉄)
※10月19日は特別開館
※10月25・26日は14時まで開館
※その他の曜日はご相談下さい
唄会
10月25日(土)26日(日)
Luca Delphi
15:00開場 16:00開演
費用 / 5000円(各日15名様)
ご予約は、メールにてお名前、人数、お電話番号を記載のうえ contact@shyousyou.comまで。
※10月1日 AM10:00よりメールにて受付開始
※ご応募が多い場合は抽選となる場合がございます。
※こちらからのご予約完了のメールをお送りして、受付完了となります。
※別途お茶代(500円)がかかります。
※同伴者1名につき、お子様お1人(高校生まで)入場可。
会場
小小
愛知県瀬戸市仲洞町36 (窯垣の小径内)
※お車などでお越しの方は、窯垣の小径駐車場(無料)をご利用ください。
お問い合わせ contact@shyousyou.com
▷▷詳細はこちら
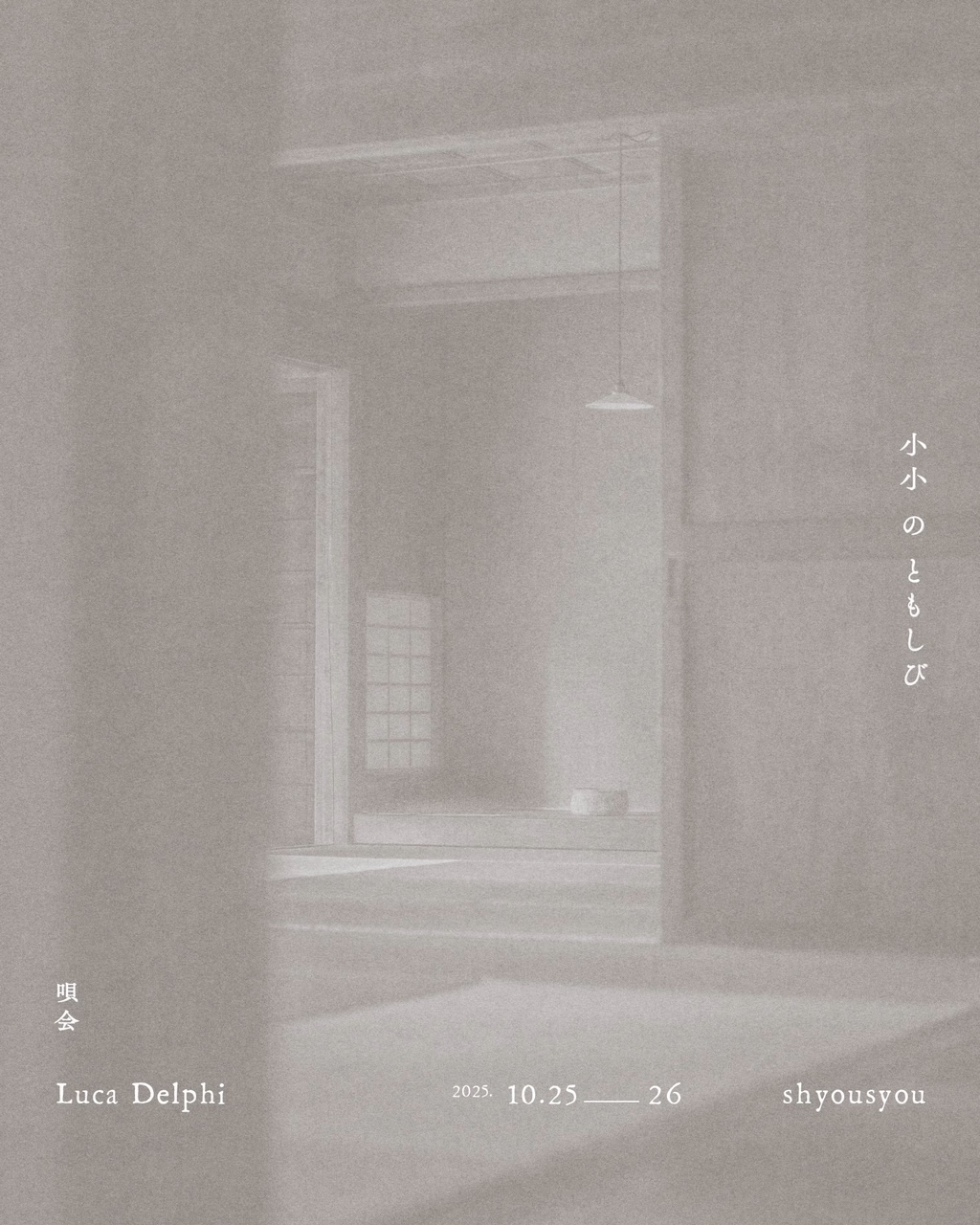

あゐ畠 at Kumihama
10月
12:00-18:00
4日(土)5日(日)
11日(土)12日(日)
25日(土)26日(日)